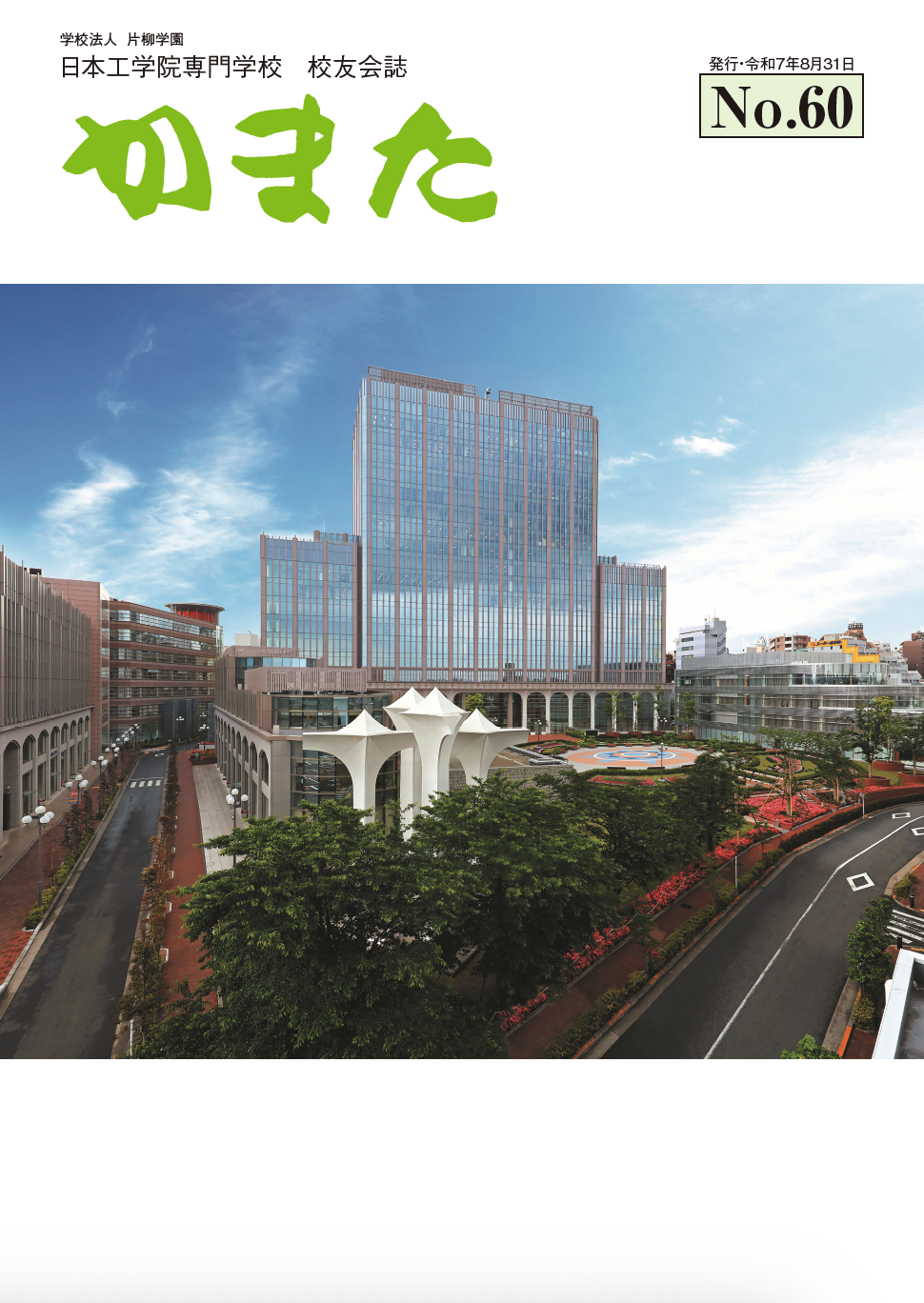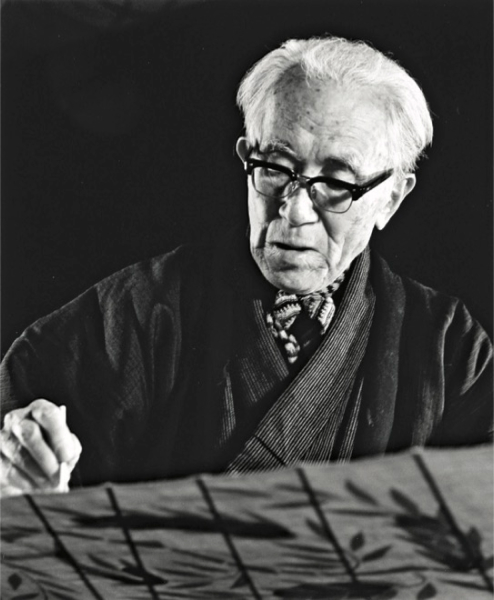■日本工学院専門学校校友会ウェブサイトをリニューアル
校友の皆さまに、より見やすく快適にご利用いただけるよう「校友会.Net」を全面的にリニューアルいたしました。
校友会や学校に関する様々な情報を掲載し、校友会誌「かまた」の最新号をカラーで公開。バックナンバーもご覧いただけるようになりました。
■第36回通常総会報告
2025年6月に開催された「日本工学院専門学校校友会 第36回通常総会」の報告を掲載しています。全国42支部を代表する代議員(支部長または副支部長)が出席し、8つの議案すべてが可決承認されました。
■支部会員の集い・同窓会レポート
2024年度に開催された「支部会員の集い」や「同窓会」の様子を紹介しています。旧友との再会、世代を超えた交流、地域ならではの話題で盛り上がった懇親会など、温かなひとときをレポートしています。